

怖い絵本ブームの火付け役として、異例の反響を得た「怪談えほん」シリーズ。
その「怪談えほん」の〈未刊の1作品〉の文章を公募した企画「怪談えほんコンテスト」の最終選考会が、2018年9月27日、岩崎書店にて開催され、審査員の宮部みゆきさん、京極夏彦さん、東雅夫さんによる審議の結果、応募総数3011作品の中から大賞となる1作品が選ばれました。
本稿では、最終選考に残った20作品の講評を含めた、選考経過をご報告します。
岩崎書店 怪談えほんコンテスト事務局

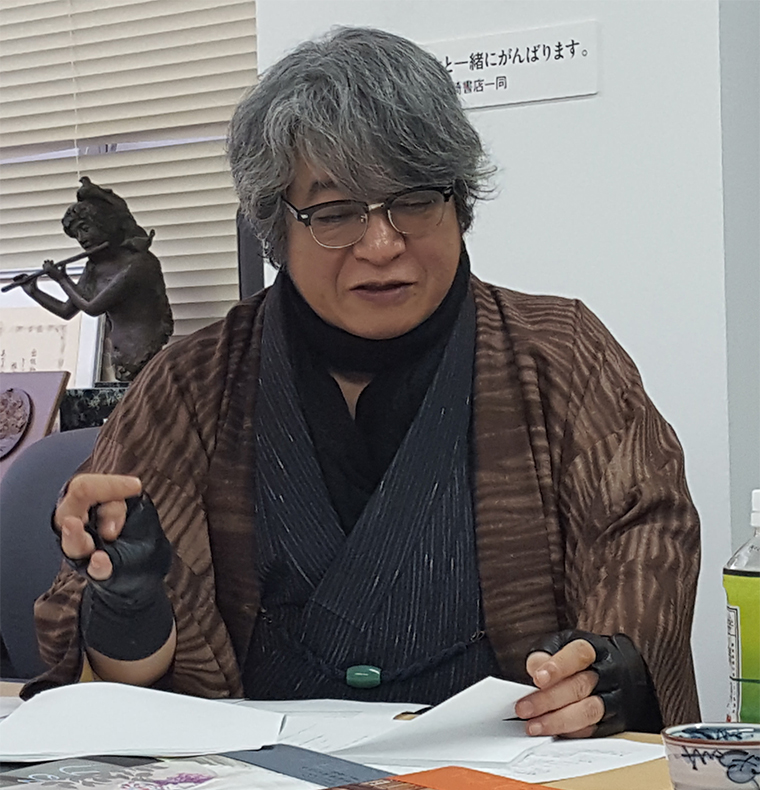


バスクリンの入った水面を鏡としているネタはおもしろかった。「のろいをなんでぼくにおしえるんだろう」というところもよい。しかし、〈むらさきのかがみ〉は有名な都市伝説なので、あっと驚く展開、あるいは、もう少しひねりがほしかった。従来の都市伝説のパターンと離れていけば、おもしろかったかも。文章も説明しすぎの感がある。
あぶないあそび系。アイデアはおもしろいが、絵本にしたときにどうか。話も少しわかりにくい。読み聞かせでは、途中で子どもの集中力が切れてしまいそう。最後のオチが、ちゃんと考えないとわからないところも、ちょっと厳しい。電話というファクターはなくてもよかった。骨子だけをしっかり残せばよくなった作品。もったいない。
自動販売機の話。〈新耳袋〉にもある。絵にするとき、最後のお母さんと子どもが一緒の場面を、ぐにゃーっとまざりあったような凄まじい姿に描いたらいいかも。文章はブラッシュアップすれば、いいものになる要素もある。しかし、構造がうまくない。ディテールでいこうとすると、絵で描けばいいことも、文章にしてしまう。つまり書きすぎてしまう。最後の決め台詞も、タイトルと同じにしたらよかったかも。
アイデアはよい、子どもが好きそうではある。が、途中でグロさが出てきてしまった。そのグロさが、最初からわかってしまった。視点が大人。子どもが喜ぶように書けてない。笑える話にした方が、最後が逆に怖くなったかもしれない。最後の4行はなくてもいいかも。嫌な感じの印象が、記憶に残る作品だった。
おもしろいが、三津田信三さんの作品に同じアイデアがある。先行作品を凌駕していればよかった。画家が、すきまを感じさせるすごい絵を描けばおもしろくなるかも。「ひとか けものか ばけものか」はなくてもよかった。具体的なものがあがってこない方が怖くなる。すきまを連発するだけで怖かったかも。場面転換が多すぎるので、絵本にするとおさまらない。
予言系。見えてしまうお話。オチがわかりにくい。感覚的にパッとわかる感じではない。考えオチ。文章的には申し分ない。しかけがもっとアピールできていればよかったかも。
ストレートにおばけ系。最終選考に残った作品中、おばけが出てくるのはこれだけ。子どもらしくてよかった。星新一さんのショートショートなどにありそう。因果関係がないところもよい。最後が伊藤潤二さんの〈首つり気球〉っぽい。黒くて丸い小さなものが、女の首だったと書くのは不自然。黒くて丸いものに顔があった、という方がよかったかもしれない。手直ししたらよくなる可能性もある。
金魚にえさをやらなかったらこうなるという教訓系。ユリは、絵にしたらきれいなものになりそう。きれいなものが実は恐ろしい、という感じはいいと思う。しかし、絵にするところを説明しすぎている。最後にネタをもっていくための説明も多い。文章が段取っているから、絵にする余白がないところが、絵本の文章としては難しい。
日常崩壊系。シュール。グロくてきれいな絵本にはなりそう。少し不思議な話。理解するのは難しいかも。絵本の語り口は、とても勉強しているように思う。構造もしっかりしていて場面が描きやすい。しかし、わかりづらいところがある。オチが難しく感じる。ラストが飛びすぎている。
日本の怪談、都市伝説のパターンをパノラマ的に見せている。そこは大人がよろこぶのでは。しかし、オチがありがち。最後は怖くないパターン。岡本綺堂の話に似たものがある。登場する怖いものが多すぎる。逆に、怖くないものが子どもには怖く見える、気配が怖い、という方がいいのでは。構造を変えると怖くなる作品。もったいない。
日常崩壊系。日常が怖い。見方によっては、ドラッグ?と思わせるあぶない話でもある。絶望系は、傑作にもなる。トラウマにもなりかねない。この作品は、怪談ではなくホラー。怪談は、終わったあとも続くから怖い。滅んでしまう、なくなってしまう話は、怪談と一線を画すのではないか。
単純な話で、怖い。子どもも砂遊びで、こういう妄想はする。しかし、文章が長い。ディテールを大人目線で書いてしまっている。大人が子ども時代のことを思い出して書いている感じ。全般、文学的。ひらがなで書いているが、言葉が難しいところが惜しい。言葉をもう少し選べばよくなる。最初の1行をラスト2行前に持ってくる構成にしたら、もっとよかったかも。
シックスセンス系。最後の1行はなくてもいいかも。余計な文章が多い。出オチ。文章だけで読む方がいい作品。絵にするのは非常に難しいのではないか。アバンギャルドな絵を、うまくつけたら、すごくよくなる可能性もある。
20作品の中で、審査員の評価点数が高かった次の7作品が、さらに審議された。
ほくろの発想はおもしろい。ほくろってなんでついてるんだろうと思う。ただ、絵が難しいかも。最後の場面、絵はどうなるんだろうと思う。かわいい絵ならOKか。〈ほくろ〉にしない方がよかったかもしれない。人にはやばい〈スイッチ〉があるという設定。ほくろだけでなく、鼻の頭とか、耳たぶとか、どこにあるかわからない〈やばいスイッチ〉がある、とするほうが、絵本としてはおもしろいのではないか。
逆シックスセンス。切ないお話でよく書けている。しかし、「みえるひと」という言葉が使ったところが、よくない。みえるひとにとっては当たり前だし、みえないひとにとっては、みえるひとが変だから。最初の3行で、こういう概念にはじめて触れる子どもに、偏ったことを教えることになってしまう懸念はあるが、絵本でみせるのは新鮮。室生犀星のお話にもあるが、死んだ子が家にいて、というところはいい。「みえるひと」みたいな言い方をせずにこの作品を書いていたら、相当よい感じだった。
さすがにプロ。おもしろい。本になったときのことを考えて書かれている。いじめはいかんという教訓系。こういうストレートなものが、怪談えほんの中にあってもいいかも。しかし長い。絵本にする「場面割」を考えると、難しい。小説になっている。このリズムで読むから怖い。しかし、絵本はページを開いて絵を見るという作業があるから、この文のリズムでは読めない。ショートショートならいい。場面を全部絵にしようとすると、マンガになってしまう。とてもいい作品だが、絵本にするには難しいのが、惜しい。
さらなる審議の結果、次の4作品が残った。
絵本として、文章量は過不足ない。点が3つあると顔に見える、というのは心霊写真の解釈だが、お母さんに説明させなくてもいいかも。お母さんに相談したら「気のせいよ」くらいがいい。最後は、『いるの いないの』の応用なのだが、このくらいひねってくれればOK。異形系。怪談ど真ん中。王道。構造もシンプルで、構成もしっかりしていて、言葉もいいのでは。
上手い。完成度は高い。怖いけど最後が前向きなところもよい。しかし、「あなた わたしが うらやましいでしょ」はいらない。ちらっとみて、「とりかえっこしない」くらいで十分。理屈はいらない。この流れなら、絵にゆだねる部分が多く、非常によい。意外なところに着地しているところもよい。
絵にしたら、描きがいがあって、すごくおもしろくなりそう。水族館で迷うというのは、いいシチュエーション。しかし、オチがちょっと説教臭い。これも教訓系だけど、金魚を殺してしまってごめんなさい、はない方がいい。水族館で迷って出られなくなってしまった、だけの方が怖い気がする。あるいは、最後、ぼくが飼っていた金魚だー!で終わりでもいい。構成を少し変えたらいいのでは。
すごいおもしろい話。変な話。何が起きているかわからないし、実際に起きたら怖い。新しい怖さだと思う。自分が沈んでいく。最後、いなくなってしまうのではなく、どうなるのかわからないところもおもしろい。異界にひっぱられたのかもしれない。沈んでいくのに、まわりが気づかないのもおもしろい。不条理であり、絵で描いてもおもしろいのでは。曜日ごとに変わっていくところに意味がある。プロセスを見ていくところがおもしろい。だれも書いていない、異界ひっぱられ系。
どれも絵をつけて見てみたい。どの作品もそれぞれによさがあり、甲乙つけがたい。
ひとことでいうと、『こっちをみてる。』は〈人面瘡〉。『とりかえっこ』は〈からだとりかえっこ〉。『ずぼ ずぼ ずぼ』は〈しずみゆくおとこ〉。『すいそう』は〈アクアリウムの迷宮〉というような感じの作品。
『とりかえっこ』は、途中でオチがわかってしまうのでは? でも、戻れないかもというところが怪談としていい。
『ずぼ ずぼ ずぼ』は、じりじりと悪い方向にいくのがいい。不条理ナンセンス絵本になって、笑いの方にいってしまう可能性もある。でも新しい。
『すいそう』は、最後の金魚のくだりが気になるが、構造を変えれば可能性があると思う。しかし、作者がどのくらいこの構造にこだわっているかによる。
現時点で、完成度が高いのは、『こっちをみてる。』と『とりかえっこ』。
これらは、大きな改編はなしで、やや変更程度でいける。読み聞かせでも、調子をつけやすそう。
『とりかえっこ』の、からだのパーツを変えるというのは、怪談ではあまりないが、絵本のお話としては、よくあるスタイル。子どもは、むしろ〈とりかえっこ〉は怖くないかもしれない。
新しいといったら、『ずぼ ずぼ ずぼ』。しかし、怪談というより愉快になってしまう懸念がある。
総合的にみていくと、怪談ど真ん中の『こっちをみてる。』か。
身近な世界でもあり、子どもになじみやすいのでは。画家も描き甲斐がある。文章も書き方が上手。
上記のような審議の結果、審査員の意見が一致し、大賞が決定した。
「絵本の文章」として考えると、絵に託せば、文章で説明しなくてもいいのだから、思い切って絵に任せられるかどうか、というところがポイントになる。
さらに、絵に託したうえで、どんな絵でもなんとかなるプロットにすることが必要。
絵本は小説とは違う、ということが本当によくわかった選考会だった。
最終まで残った20作品は、すべておもしろかった。
大賞を受賞した、となりそうしちさんの『こっちをみてる。』は、審査員の宮部みゆきさん、京極夏彦さん、東雅夫さんが、「演出しがいがある」と絶賛した作品。
「怪談えほん」の1冊として、プロの画家による絵をつけて出版されるのは2020年の予定です。
怪談えほんファンの皆さま、引き続きご期待ください。
怖い絵本ブームの火付け役として、異例の大きな反響を得た「怪談えほん」シリーズ。〈第1期〉と〈第2期〉で計10作品を刊行するところ、諸般の事情で1作品が欠けてしまいました。
この「未刊の1作品」を期待する声が、読者のみならず、書き手からも続々寄せられたことから、新たな書き手を迎えて生み出そうという企画が「怪談えほんコンテスト」です。
この方針で募集したところ、予想を大きく上回る3011作品が寄せられました。
| 募集期間 | 2017年12月1日~2018年6月30日 |
|---|---|
| 応募点数 | 3011作品 |
| 選考経過 | 第一次選考 3011作品⇒98作品(2018.07.25特設サイトで発表) 第二次選考 98作品⇒20作品 (2018.08.24特設サイトで発表) 第三次選考 20作品事前審査 最終選考会 20作品⇒大賞1作品 (2018.9.28特設サイト・PR TIMESで発表) |
「怪談えほん」シリーズの〈未刊の1作品〉の文章を公募した企画。
大賞作品は、プロの画家による絵をつけて、「怪談えほん」の1冊として、岩崎書店より出版。